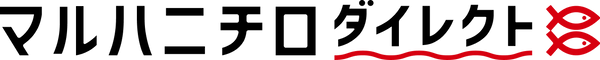「完全養殖本まぐろ」の軌跡
Share
貴重な海洋資源を未来へつなぐ、マルハニチロの30年にも及ぶ挑戦。
江戸時代から日本人に愛され続けるまぐろは、近年世界的な人気の広がりや漁獲規制の強化によって、将来にわたる安定供給が不安視されています。そうした時代の流れを予見し、マルハニチロでは1987年に本まぐろ(クロマグロ)の人工種苗生産の研究をスタートしました。それまでのまぐろ養殖は、漁獲した若い天然まぐろを育てて大きくするもの。一方、マルハニチロが目指すのは、人工的にふ化させたまぐろを親魚に育て、その親魚が生んだ受精卵をふ化させ、稚魚から成魚に育てる「完全養殖」。天然資源に負荷をかけず、魚食文化を未来へつなげようというマルハニチロの挑戦が、ここから始まりました。 完全養殖の拠点、奄美大島養殖場全景
完全養殖の拠点、奄美大島養殖場全景
まぐろの生態を知るところから始まった完全養殖への挑戦は、大量生産というハードルの前に一時中断を余儀なくされたものの、2006年には事業化に向けて再スタートを切りました。2008年には複数の大学と組んで共同研究を行うことになり、民間企業だけでは難しい基礎研究もこれを機に一挙に加速していきました。完全養殖のための舞台に選ばれたのは、奄美大島の2つの養魚場。もともと真鯛の稚魚を生産していた奄美大島は、養殖のノウハウを有していたことに加え、入り江に囲まれた穏やかな環境がまぐろの養殖に最適と評価されました。
 ふ化した稚魚は約6cmの種苗になるまでふ化場で育成
ふ化した稚魚は約6cmの種苗になるまでふ化場で育成
まぐろの産卵のシーズンは6月〜8月。この時期には日々顕微鏡で卵質をチェックし、頃合いをみて採卵チームが生け簀から卵を集め、ふ化場に運びます。採卵からふ化までのプロセスをクリアした後にぶつかった新たな壁は、稚魚を育てる難しさでした。
 奄美大島のスタッフは日々船上から成育を見守る
奄美大島のスタッフは日々船上から成育を見守る
自然の海で、まぐろが成魚になる確率は、何十万粒の卵からわずか数尾。まぐろの稚魚は振動や音、光に敏感で、施設の電気をつけた途端、驚いて水槽の壁に衝突してあっけなく死んでしまうことも。さまざまなリスクから繊細な稚魚を守るために、共同研究者とスタッフの創意工夫が続けられました。関係者が一丸となった努力は、2010年、民間企業として初となる完全養殖成功に結びつきました。
 奄美大島にある完全養殖本まぐろの生簀
奄美大島にある完全養殖本まぐろの生簀
 大型の生簀が整然と並ぶ大分のアクアファーム
大型の生簀が整然と並ぶ大分のアクアファーム
体長6cmほどの「種苗」になるまでふ化場で大切に育てられた稚魚は、その後全国5ヵ所の養殖場へ運ばれます。養殖場では、まぐろがストレスなく泳ぎ回れるよう、国内最大級の大型生簀を採用。可能な限り自然に近い環境で、栄養バランスに配慮した飼料を与えられたまぐろは、約3年後出荷の時を迎えます。
 取り揚げられたまぐろは約一週間で奄美大島から食卓へ
取り揚げられたまぐろは約一週間で奄美大島から食卓へ
50kg前後に育ったまぐろは「BLUE CREST」のブランド名が付けられ、皆様の食卓へ。 手塩をかけた完全養殖本まぐろの美しい身には、天然まぐろに引けをとらない濃厚な旨みとともに、海洋資源を未来につなげるマルハニチロの決意と情熱が詰まっています。
2018年9月3日配信